今回は、様々な加熱温度によって起こる牛肉への影響について、詳しく解説していきます!
この記事では、加熱温度によって起こるタンパク質の変性や、色と食感の変化、食品安全などについて掘り下げて紹介していきます!
タンパク質の変性と水分損失
牛肉を加熱すると、筋繊維を構成する主要なタンパク質であるミオシンとアクチンが熱変性を起こし、肉の組織構造と水分保持性が変化します。
低~中温度域(~50~60℃)では、まずミオシンが変性・凝集して筋繊維が収縮し始め、肉は生の柔らかい状態から少し締まった食感へ変化します。
この段階では細胞から一部の水分が絞り出されますが、中心温度が約50℃程度までの「レア」の範囲であれば肉汁の大部分は保持されており、内部は非常にジューシーです。
一方、より高温(~66℃以上)になるとアクチンが66~73℃程度で変性し始め、筋肉繊維がさらに強く収縮します。
この高温域では筋繊維から水分が一気に押し出され、肉汁の損失量が大幅に増加します。
このため、ウェルダン(中心高温に火を通した状態)では肉がぱさつきやすく、噛み応えも硬く感じられます。
筋繊維内の水分が逃げ出すことで、加熱中の肉からは肉汁が表面に滴り落ちたり蒸発したりします。
特に内部温度が60℃前後に達する頃、肉からは「浸出液」が急激に増え始め、目に見えて身が縮む現象が起こります。
これは筋線維間の結合組織(コラーゲン)が熱で収縮し、水分を押し出すためです。
加熱温度が高くなるほどこの水分損失は大きくなり、過度の加熱によって肉が乾燥してしまう主因となります。
なお、調理後に肉を休ませる(いわゆる「レスト」を取る)ことで、筋繊維内の凝固したタンパク質が多少ゆるみ、逃げ出した肉汁を部分的に再吸収することができます。
ミオシン由来の収縮は多少戻せるものの、アクチンの変性による水分損失は不可逆であるため、休ませても完全に失われたジューシーさが戻るわけではありません。
したがって、肉をジューシーに保つには適切な温度で加熱を止めることが肝心です。
色と食感の温度変化(レアからウェルダンまで)
肉の色変化は主に色素タンパク質であるミオグロビンの熱変性によるものです。
牛肉の場合、内部温度がおおよそ60℃に達するとミオグロビンが変性して赤色から褐色へ変わり始めます。
このため、中心部まで加熱したウェルダンの肉は灰褐色である一方、中心温度が低いレア・ミディアムレアの肉は赤みやピンク色が残ります。
食感の面では、内部温度が50℃台までの肉は柔らかくしっとりしています。
ミオシンの凝固によって適度な弾力が出ますが、水分保持性はまだ高いためです。
しかし65℃以上になるとアクチンの変性収縮で急激に硬さが増し、水分の抜けた筋繊維は噛み切りにくくなります。
このため、ミディアムより上の火の通し加減(ミディアムウェル~ウェルダン)では肉質が格段に硬く、噛みごたえのあるものになります。
興味深いことに、筋肉中のコラーゲン(結合組織)は約60℃付近で一旦収縮して肉を締め付けますが、さらに高温に達すると徐々に分解が進みます。
70℃を超える温度で長時間保持すると、コラーゲンは熱で変性してゼラチンに変わり始め、筋繊維同士の接着が緩んでほぐれやすくなります。
ウェルダン以上に加熱した肉でも、長時間かけてコラーゲンがゼラチン化すると繊維の間に潤い成分が生まれ、ホロホロと崩れるような柔らかさが出てきます。
ただし筋繊維そのものは既に水分を失い硬く縮んでいるため、ゼラチン化による「柔らかさ」はいわば結合組織の接着力が切れたこととゼラチンの保湿効果による見かけ上のものです。
風味(フレーバー)の変化
肉の「風味」は加熱温度と密接に関係しており、特に高温での調理によるメイラード反応が大きな役割を果たします。
肉の表面温度が約140℃以上になると、筋肉中のアミノ酸と糖が反応するメイラード反応が活発に進み、きつね色の焼き色とともに香ばしい風味を持つ褐色物質(メラノイジン)が生成されます。
ステーキやローストビーフの表面にできるこんがりとした茶色の焼き目は、このメイラード反応によるもので、肉に典型的な食欲をそそる香り(いわゆる「肉らしい香り」)を生み出します。
焼肉やステーキから立ち上る香ばしい匂いは高温調理によって初めて生まれるものであり、低温でゆっくり加熱しただけでは得られません。
そのため、低温調理を行った肉でも仕上げに表面を強火で焼き付けるのは、この風味を引き出すために重要です。
また、肉に含まれる脂肪も加熱による風味と食感に影響します。
牛肉のサシ(脂肪交雑)はおおよそ52~54℃付近で溶け始め、肉の中にジューシーで滑らかな食感を与えます。
適度に加熱された脂肪は旨味成分を閉じ込め、口当たりを良くする潤滑油のような役割を果たします。
特に和牛のように豊富な脂肪を含む肉では、脂肪が十分に融解する温度まで火を入れることで肉全体の風味が増し、コクのある味わいになります。
一方で、加熱が進みすぎると脂肪が流出して肉から抜け落ちたり、焦げて苦味のもとになることがあります。
したがって、強火で香ばしさを引き出しつつも脂肪を焦がしすぎないように調理温度と時間を調節することが、美味しい風味を得るコツです。
調理方法によって風味の出方も異なります。たとえば茹でる・煮る調理では、肉を高温の湯やスープで加熱するため表面が140℃以上になることはなく、メイラード反応による焼き色や香ばしさはほとんど付きません。
その代わり、肉の旨味成分が煮汁に溶け出しスープやソース自体に風味が移るため、茹でた肉単体では淡泊な味わいになりがちです。
一方、焼く・ローストする調理では、表面に高温の乾いた熱が加わり香ばしい焼けた風味が肉自体に残ります。
調理目的に応じて、茹でて出汁を取るのか、焼いて香りをつけるのかを使い分けることが、風味面でのポイントになります。
食品安全と加熱温度
肉を安全に食べるには、加熱により食中毒菌を死滅させることが重要です。
牛肉の場合、表面に付着した細菌(腸管出血性大腸菌O157やサルモネラ属菌など)が主なリスクですが、ひき肉やタタキのように肉を細かくした製品では細菌が内部まで入り込むため、より高い温度まで中心部を加熱する必要があります。
多くの病原菌は75℃で1分以上の加熱によって死滅することが知られており、厚生労働省も「中心部まで75℃で1分間以上」の加熱を食肉調理の基準としています。
これは同等の殺菌効果として「63℃で30分」加熱するのと同じ水準であり、安全のためはいずれかの条件を満たすことが望ましいとされています。
具体的な温度ガイドラインとして、日本ではハンバーグなどのひき肉料理は中心温度75℃以上で1分間の加熱が推奨されています。
米国の食品安全基準でも、ステーキなどの塊肉は中心145°F(63℃)で最低3分間保持(余熱でも中心温度を維持)すること、ひき肉料理では160°F(71℃)以上まで加熱することが定められています。
ステーキなどの塊肉をレア気味に調理する場合は、表面を高温で焼いて外側の細菌を十分に殺菌することが前提となります。
一方、ローストビーフなど厚みのある塊肉を低温で時間をかけて調理する場合や、真空低温調理(スーヴィド)の場合は、上記の時間と温度の組み合わせで中心部まで加熱殺菌することが重要です。
例えば中心温度を55~60℃程度に抑えて長時間調理する場合でも、所定の時間保持すれば菌の数を安全なレベルまで減らすことが可能です(例:63℃で30分、60℃なら約2時間以上保持する)。
いずれにせよ、食肉を扱う際は中心温度を測れる温度計を用い、安全基準を満たしていることを確認することが望ましいでしょう。
なお、肉の色だけで加熱の十分さを判断するのは注意が必要です。
挽肉は加熱しても内部がピンク色のままになる場合があり(特に事前に酸素に触れて変色している場合など)、逆に十分加熱されていなくても表面が茶色く変化することがあります。
そのため、特にハンバーグなど中心まで火が通りにくい料理では、見た目に惑わされず温度基準で判断することが安全策と言えます。
長時間加熱(煮込みや低温調理)の効果
調理温度だけでなく加熱時間も肉質に大きな影響を与えます。
比較的低めの温度で長時間加熱する調理(例:煮込み料理や真空低温調理)は、短時間で高温調理する場合とは異なる変化を肉にもたらします。
煮込み(ブレージング)では、液体中で肉を沸騰に近い温度(約90~100℃前後)で何時間も加熱します。
例えば牛すね肉やブリスケット(胸肉)のような硬い部位も、2~3時間かけて煮込むとコラーゲンが溶け出してゼラチン化し、ほろほろと崩れる柔らかさになります。
これは前述の通り、高温で長時間加熱することで結合組織中のコラーゲンの分解が進み、筋繊維を束ねていた硬いネットワークが崩壊するためです。
煮込み料理では肉そのものからは水分が抜けてパサつきますが、溶け出したゼラチンや煮汁が肉を覆い、しっとりと感じさせてくれます。
いわゆる「箸でほぐれる」ような食感は、このゼラチン化した結合組織によるところが大きいのです。
一方で、煮汁に肉の旨味成分が溶け出しているため、肉単体の風味は煮汁と一体で味わう形になります。
長時間の煮込みによって得られる柔らかさと風味は、短時間の高温調理では再現できない特徴と言えます。
真空低温調理(スーブィット調理)では、食肉を密封パックし水槽などで比較的低い温度(50~70℃程度)を長時間保ちながら加熱します。
低温でじっくり加熱する最大の利点は、水分損失を最小限に抑えつつ肉を軟化できることです。
例えば筋の多いチャックロール(肩ロース)でも、55~60℃程度で何十時間も加熱すれば、内部はピンク色のミディアムレアに近い見た目のまま柔らかく食べやすい状態にできます。
実際、55℃はコラーゲンが徐々に変性を始める下限温度ですが、この温度では変性速度が遅いため非常に長い加熱時間が必要です。
温度を少し上げて60~65℃にすればコラーゲンの分解は速く進み、より短時間(数十時間程度)で目的の軟らかさに到達します。
一方、加熱温度を低く抑えることでアクチンの変性を防げるため、筋繊維からの水分流出が少なく、ジューシーさも維持されます。
つまり低温長時間調理は「肉汁の保全」と「結合組織の軟化」の両立を図る調理法と言えます。
ただし、極端に長時間加熱すると肉の酵素的な作用やタンパク質分解が進みすぎて食感が mushy(ドロドロ)になる場合もあり、適切な時間設定が重要です。
低温調理では、加熱中の肉自身の酵素が軟化に寄与する点も見逃せません。
肉にはカルパインやカテプシンといったタンパク質分解酵素が含まれており、これらは約40~50℃まで活性を保ちます。
ゆっくり加熱してこの温度帯を経過させると、調理中にも酵素が働いて筋肉を部分的に軟らかくする「熟成」のような効果が得られます。
低温調理では加熱開始から内部が50℃程度に達するまで比較的長い時間がかかるため、この酵素による軟化作用も肉質にプラスに働きます。
ただし安全のためには、狙った温度に達した後さらに一定時間保持して中心部まで殺菌する必要があります。
例えば真空調理で厚みのある肉塊を58℃で加熱する場合、十分な殺菌には数時間の保持が必要ですが、これは家庭用の低温調理器メーカーからもガイドラインが示されています。
実際、日本の低温調理ガイドでは「厚さ2cmのステーキ肉をミディアムレアに仕上げるには58℃で2時間加熱する」といった目安が提案されています。
このように時間と温度を組み合わせることで、低温でも安全かつ美味しい調理を達成できます。
ステーキ・グリル(直火焼き)
厚切りステーキなどを焼く場合、表面に高温の火を当てて香ばしい焼き色を付けつつ、内部はお好みの火の通り加減に調整します。
内部の目標温度は、レアで約50~55℃、ミディアムレアで55~58℃程度、ミディアムで58~62℃程度が目安です。
厚みや肉質にもよりますが、これ以上高くなると急速に肉汁が失われ硬くなるため、美味しさと安全性のバランスを考えて火を止めます。
焼き上がったらアルミホイルなどで数分休ませる(肉をレストする)と、肉汁が落ち着き全体に行き渡るのでよりジューシーに仕上がります。
ロースト(オーブン焼き)
大きな塊肉(ローストビーフなど)をオーブンで焼く場合、中心部の狙い温度はステーキ同様に部位や好みに応じて設定します。
柔らかい赤身肉の塊なら内部55~60℃前後のミディアムレアで仕上げるとしっとり柔らかく 、薄くスライスして提供するのに適しています。
調理方法としては、最初に高温(200℃程度)のオーブンやフライパンで表面を焼いてから低温(120~150℃程度)のオーブンでゆっくり内部まで火を通すと、肉汁の流出が少なく均一に加熱できます。
ローストでは予熱で中心温度が数℃上昇することも考慮し、目標より少し低めで取り出して休ませるのがコツです。
煮る・煮込み料理
カレーやシチュー、ポトフのように煮込みで肉を加熱する場合、液体の沸点付近(約90~100℃)まで肉の温度が上がり、完全に火が通ったウェルダン以上の状態になります。
長時間煮込むほどコラーゲンがゼラチン化して肉はほぐれるように柔らかくなりますが、その反面、筋繊維から抜け出た水分は煮汁に移行するため肉そのものはぱさつきやすくなります。
煮込み料理では加熱中にアク(タンパク質由来の灰汁)を取り除きつつ、必要に応じて水分や調味料を足して煮詰まりすぎないよう管理します。
肉の安全性については、煮込み調理中は常に100℃近い高温で加熱されているため食品衛生上のリスクは低く、比較的安心して調理できます(その代わり低温調理のような温度管理の厳密さは要求されません)。
低温調理(真空調理)
専用の低温調理器(スーヴィドマシン)などを用いて、肉を指定温度の湯せんで長時間加熱する手法です。
例えばステーキ用の肉をミディアム程度に調理したい場合、真空パックした肉を55~60℃の水槽で1~2時間程度保持すると中心まで均一に熱が入り、狙った温度以上には上がらずに済みます。
この方法では肉汁の流出が最小限に抑えられ、非常にジューシーで柔らかい状態に仕上がります。
ただし前述のとおり、低温では細菌が瞬時には死滅しないため十分な加熱時間の確保が不可欠です。
低温調理後は袋から肉を取り出し、水気を拭き取ってからフライパンやバーナーで表面を短時間焼き付けて仕上げます。
これにより、内部はしっとりとしていながら表面に香ばしい風味を持つ絶妙なステーキを作ることができます。
低温調理法は家庭でもプロのような火入れ加減を再現できる手法ですが、食中毒予防のためガイドラインに沿った温度と時間を守ることが大前提となります。
まとめ
本記事では、加熱温度の変化による、牛肉の状態への影響について紹介しました!
牛肉の加熱による変化は多岐にわたり、低温では酵素作用やミオシンの凝固による優しい変化、中温域でのミオグロビンの変性による色変化、そして高温でのアクチン変性・コラーゲン収縮による硬化と水分損失が主なポイントです。
それぞれの温度帯で肉質・風味・安全性に与える影響が異なるため、調理の目的に応じて適切な温度管理を行うことが求められます。
例えば「できるだけジューシーに仕上げたいなら低~中温で止める」「コラーゲンの多い肉を柔らかくするには高温で長時間煮込むか低温で非常に長時間加熱する」「食中毒を防ぐには所定の温度まで加熱する」といった判断が必要です。
それぞれ科学的な裏付けを理解することで、牛肉調理のクオリティと安全性を両立させることができるでしょう。
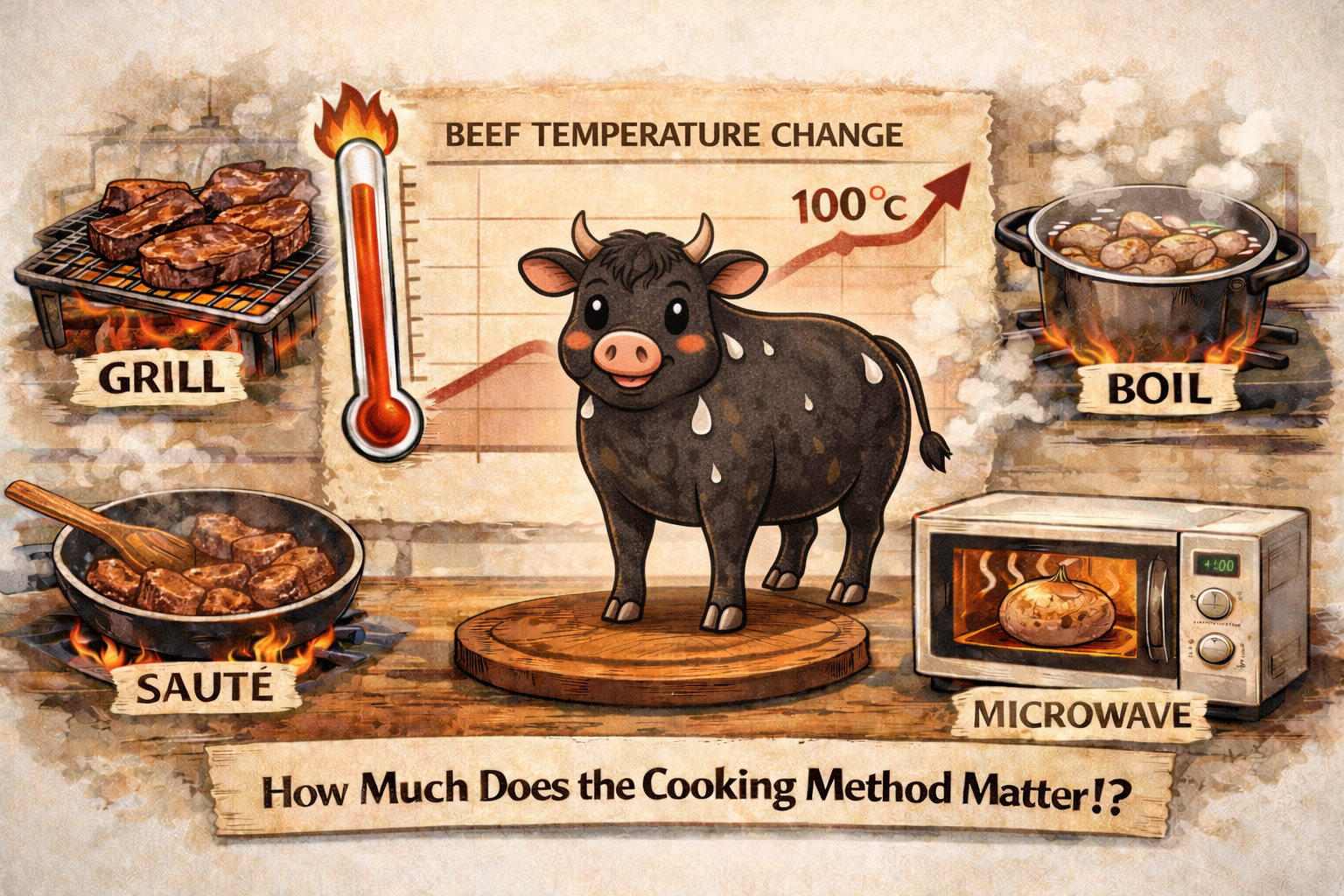

コメント